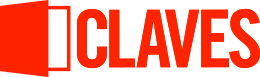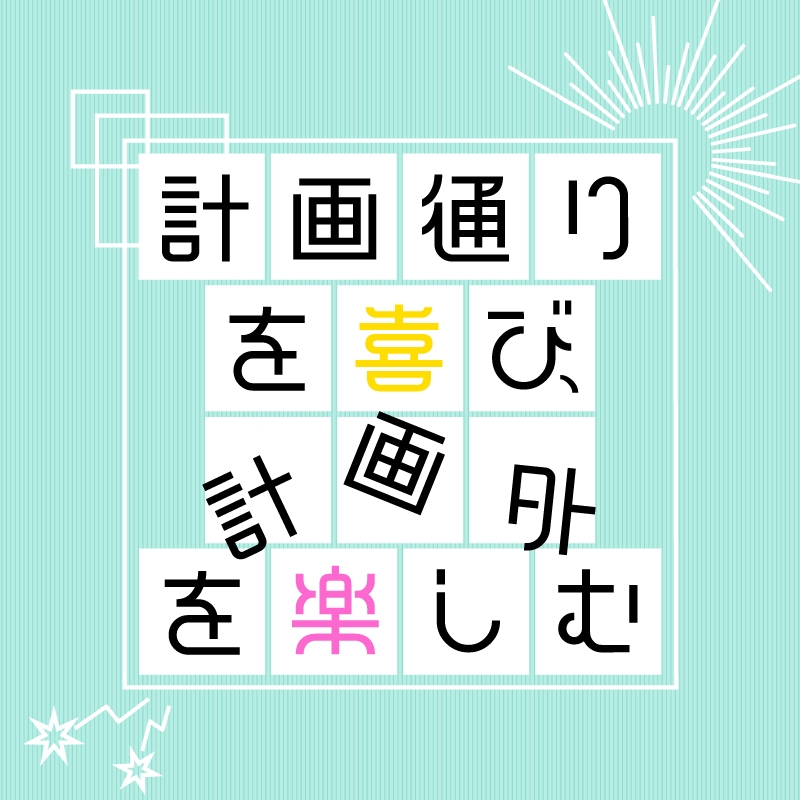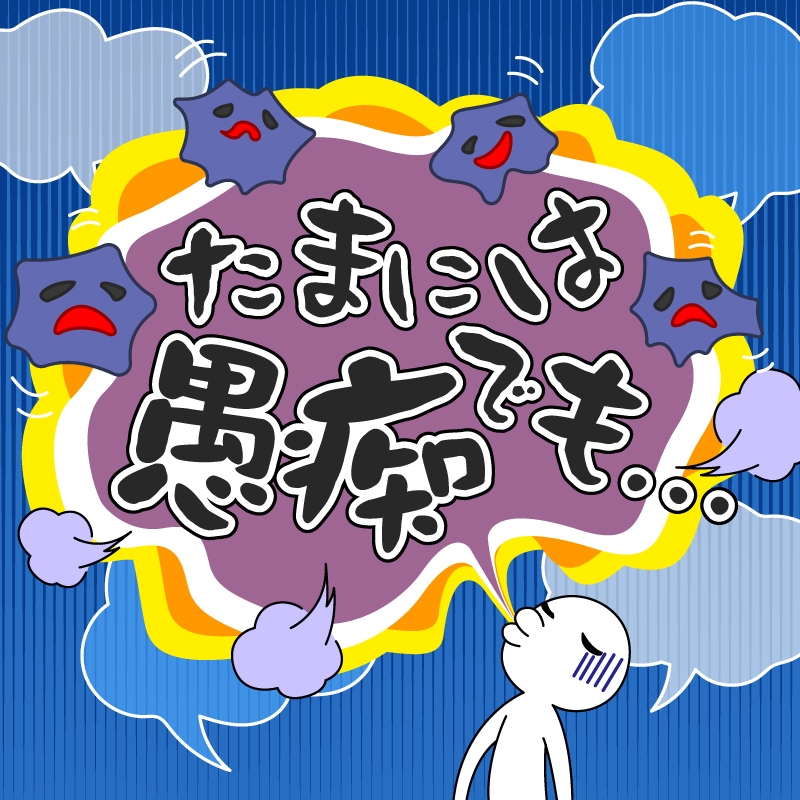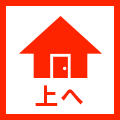
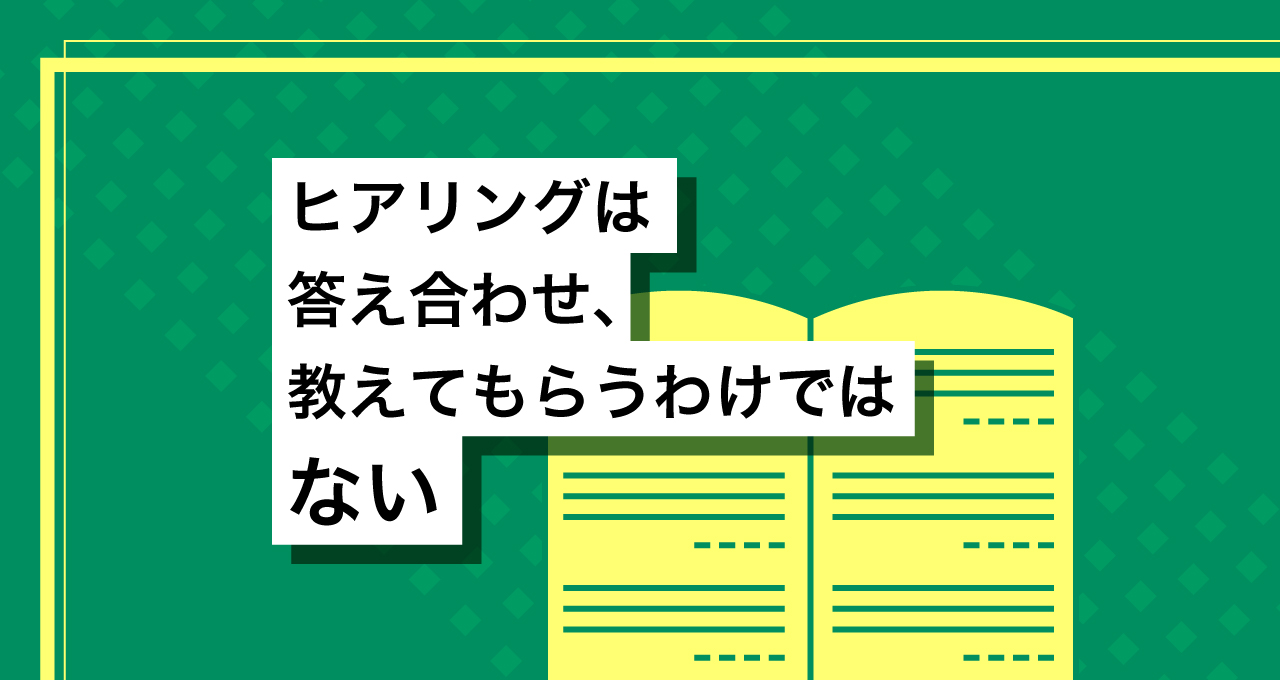
どうも、堀内です。
自分の手から離れているプロジェクトや、そもそも入っていないプロジェクトの状況確認、または相談で入ることがあります。
その際に、方針がなんだか理想的ではないなと感じた時に、「どのように考えたのか?」「経緯は?」と確認することがあります。
クラベスでの仕事において、私が大事にしていることがあります。それは「良いものを作る(正しいものを作る)」「言われたものをそのまま作らない」ということです。
最初は採用向けの会社説明に書いていましたが、お客様向けの提案資料にも載せることにしました。
お客様はシステムに関しては、基本的には素人であり、私たちがプロであると考えます。
お医者さんに「ここが痛くて」、「ここが悪くて」と相談はできますが、「この薬がほしいです」とは言いませんよね。

お医者さんも「この症状にはこのような手段が取れますが〜」という話はしてくれるケースがありますが、最初から「Aという薬とBという薬がありますが、どうしますか?」という質問はしません。
お客様に選択肢を提示して選んでいただくことは良いと思っていますが、選択肢を提示することが、良い対応だと思われては困ります。
最適な解は我々側が持っているべきで、その中でも運用によって変更しても良い点や、ブランド的な見せ方、操作者の理解度などで調整できる部分についてはお話を聞くのは良いと思っています。
最初に症状や困っていること、実現したいこと、叶えたいことをヒアリングする時は、自分がその担当者と同じ気持ちになれるくらいヒアリングをしてほしいです。その中で、自分の知識と交えながら理想像を作り上げていきます。
さらにいうと、ヒアリングの前の事前情報で、お客様の理想的な姿をぼんやり想像します。
その理想像とのギャップをヒアリングで確認し、理想像を修正したり、理想へ近づけるためのアプローチを取っていきます。
お客様が不安に思っていることをヒアリングするのもよいですが、その不安を直接解消するようなアプローチよりも、理想的な動きにすればその不安は拭い去れますね、というアプローチにしたいです。
我々はシステムの専門家であり、お客様はそのお客様の業務の専門家です。
業務について教えてもらうのは良いのですが、どのようにシステムを作るのか、については教えてもらう必要はありません。
もし、一言一句お客様が話せるのであれば、もうこの時代ではAIを使って作ることができます。
我々もコーディングにおいてAIを使っていますが、全てを任せるわけではなく、要点の確認や効率化を目指して使っている段階です。
我々は最終的には、お客様にとってシステムに関するコーディネーターや主治医のような立ち位置になっていくのではないかと考えています。
システムが有ることが当たり前になった世の中です。AIが当たり前の世の中になっていきますが、パソコンやスマホが出てきた時と同様に、うまく使いこなしていくことが大事です。

そのためにも正しいヒアリングを行い、理想像を考え、アプローチすることが重要です。
この理想像を考えずに、目の前の選択肢のみに終始するコミュニケーションをしていたら、今すぐ見直してください。
リーダーやディレクターが持っている理想像と、メンバーが持つ理想像のすり合わせも必要で、お客様との理想像のすり合わせも大事です。 この理想像を共有するためにも、言語化、資料化、コミュニケーションが重要になります。
多くの人はこのアプローチをしていないので、今できていないことに気がついたのであれば、そこに一歩踏み込む勇気を出してみてください。
理想像を思い描かないと良いものは作れないので。
ではまた。
2025.08.29 (夏の終わりの歌って結構ありますよね)